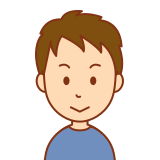
病院薬剤師として働きたいけど、どんな病院を選べばいいのかな?
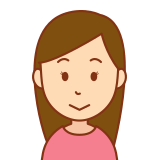
実習に行って病院で働きたいと思ったけど。求人も少ないし無理かな。
アンサング・シンデレラで注目が集まった病院薬剤師。
薬剤師として働くにあたり就職先にどこを選ぶかは人生の岐路でもあるので慎重に判断したいですよね。
病院薬剤師として就職先を選ぶときのポイントについて解説します。
【この記事を書いた人】

調剤薬局を2年経験後、病院薬剤師に転職しました
薬剤師として成長するには

薬剤師の資格をとったらまずやるべきことがあります。
それは自分の理想とするロールモデルを見つけること
いまはSNSで情報収集できるので、薬剤師として成長するのに病院だから、薬局だから、という時代ではありません。
活躍している人はどんな環境にいても活躍しているわけなので。
なので薬剤師として成長したいと思うなら、まずは自分の理想とするロールモデルを見つけることが大事です。
学生なら実習先で出会った薬剤師、すでに働いている人なら上司や同僚、もしいなければ学会などに参加することで、自分のロールモデルと言える人に出会えるかもしれません。
病院薬剤師であるメリットは?
次に置かれた環境でできることを上手に活用していきます。
病院薬剤師には病院薬剤師ならではのメリットがあります。
私が個人的に病院薬剤師になって良かったな~と思うことを挙げてみます
医師を含む医療スタッフと話ができる
言い換えれば全人的な医療に参加できるということでしょうか。
私は調剤薬局→病院に就職しましたが、真っ先に最初に驚いたのは医療用語に全然ついていけなかったことでした。特に検査値が全然分かりませんでした。
今では調剤薬局でも検査値見るのは当たり前になりつつありますが、医療用語が分からないとその他の職種とも話ができません。
患者さんの病気の治療は医師だけでみているわけではないので、看護師、検査技師、放射線技師、リハビリ(ST、OT、PT)、ソーシャルワーカー、心理士、病院事務職員、訪問介護ステーション、調剤薬局など多くのスタッフと関わることで、多面的な視点の大切さが分かります。
もちろんこれは病院に限ったことではないですが、普段から多様な職種と交流ができて、がん・感染・NST・褥瘡・摂食嚥下・緩和ケア・周術期など多職種専門チームで活動できるのは病院のメリットだと思います。
病態がわかる
病院に入るまで分からなかったんですが、病態が分かると一気に医学・薬学が面白いと思えてきます。
処方の根拠が見えてくるんですよね。
カルテは情報の宝庫ですし、直接医師とディスカッションすることで医師の思いが分かります。
調剤薬局時代には処方箋の薬と患者さんからの聞き取りだけで病態を把握しないといけなかったので、ここは結構な壁でしたね。
今でも知らないことが山ほどあるので、日々是勉強です。
薬剤師って捨てたもんじゃないと思える
専門薬剤師制度が立ち上がって、各分野でスペシャリストがいます。
彼らの知識は半端ないです。全国には医師とも堂々と渡り合える薬剤師って本当にいるんですよ。
さんざん薬剤師不要論が囁かれてますけど、世の中にはすごい薬剤師がたくさんいて、薬剤師ってまだまだ捨てたもんじゃない、って思えたのも病院薬剤師になって良かったなと感じることです。
失敗しない病院の選び方

では、病院の就職先を選ぶときに失敗しないようにするにはどうすればよいのか?
私がもし学生の立場だったらやってみたいことを挙げてみます。
手当たり次第病院見学してみる
気になるところはとりあえずコンタクトを取ってみましょう。
職場環境、休憩場所の雰囲気、薬剤部の理念、勤務体制、残業時間、職員の年齢構成、認定薬剤師の数、産休・育休の取得状況など聞いてみましょう。
例えば、「薬剤師にとって一番大切なことは何ですか?」「薬剤部で大事していることは何ですか?」という質問を投げかけてみると、それぞれ病院によっていろんな答えがあって面白いかもしれません。

私の知り合いは実際にこうして、アリかナシかを決めたと言っていた(^^;
また、病院の経営状況は基本給やボーナスに直結するので大事。
経営母体はどこ?公的?民間?ボーナスはどれくらい支払われるの?経営はうまくいっている?
診療報酬の構造上の問題もあり、黒字化している病院って少ないのですが、経営母体が大きいと病院単独ではなくグループで補っているので安心感はあります。
病院薬剤師は他の就職先と比較して収入が低いと思われがちですが、けっこう経営母体によって違っていて、専門手当がついたり、昇給がきちんとされていれば他と引けを取らない職場もあります。
友達に実習先の印象を聞いてみる
学生実習に行った友人がいれば直接病院の印象を聞いてみましょう。
長期間実習していれば休憩中の職員同士の雰囲気も分かりますし、意外な内部の裏事情も聞けるかもしれません。
学会発表に積極的か、新人教育カリキュラムがあるか調べる
アクティブな薬剤師がいる職場は職場全体に勢いがある可能性が高いので、スキルアップができるかどうかの判断材料になります。
薬剤師関連の学会や論文をネットで検索すれば、希望の病院がヒットしてくるのか、どんな分野で活躍している薬剤師がいるのかわかります。
また、新人教育がしっかりしている病院は独自のカリキュラムを持っています。
教育カリキュラムを持っていることは就職の際の安心材料になりますので、公開されている情報もどんどん参考にしましょう。
とにかく自分をアピールしておく
もし希望する病院に募集枠がなくても、とりあえず自分をアピールしておきましょう。
病院は人手不足です。人気のある病院でも何らかの都合で辞めていく人はいるはず。
ネット上で募集がなくても、タイミングによって個人的なつてを介して誘いが来ることは十分考えられます。

世の中の流れ的に、特に地方の病院薬剤師は足りていません。
ここを逆手にとって将来のために自分を売り込んでおくのはアリ。
転職求人サイトを使う
個人で動くのが不安であれば転職求人サイトを利用しましょう。
もちろん個人的な「つて」も使いつつ、求人サイトを併用するのもOK。
転職エージェントは履歴書の作成や面接対策、あなたに合う求人を無料で紹介してくれます。
今の職場で働きながらでリスクは全くないですし、2-3社登録しておけばチャンスが来やすいでしょう。
ただし、良い求人はすぐに無くなってしまうので、見逃さないよう登録だけでもしておきましょう。
リクナビ薬剤師まとめ
病院選びのポイントについてまとめました。
病院薬剤師は大変、やりがいだけでは食べていけない、と敬遠されがちですが、私個人的にはそんなことは全くなく、ライフワークバランスも取れた職場で働けています。
医学・薬学を志すなら、長い薬剤師人生のどこかで病院薬剤師を経験しておくのはその後のキャリアに役立つはず。
失敗しない病院選びの参考になれば幸いです。



コメント